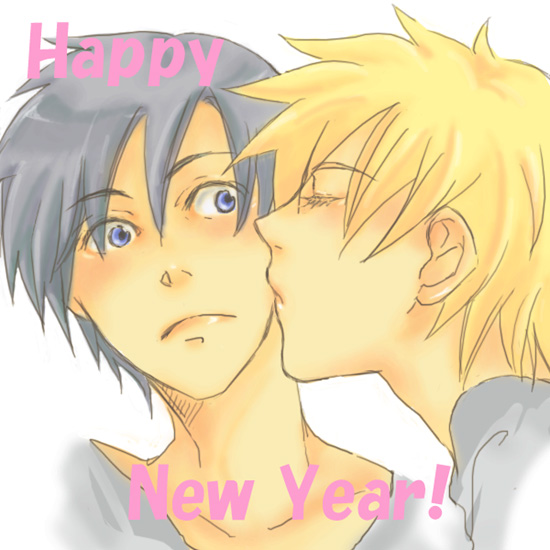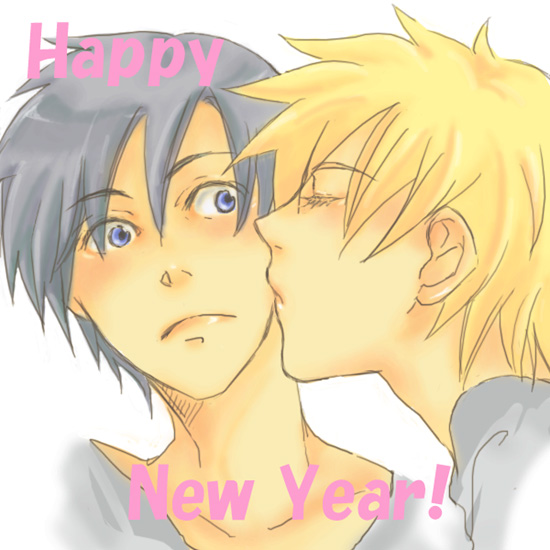「………っ!?」
今年もよろしくな。
そんな声が聞こえて、振り返ろうとした瞬間。
頬にふわりとした感触があって、僕は固まった。
着替えの途中だった僕の手の中から、服がぱさりとすり抜けていく。
「サ、サササ…サトリっ!」
「ん?」
昨夜は3人で日付が変わる頃まで騒いでいた。
年に一度の無礼講。
ルーナが部屋に戻ってからも、遅くまで二人で杯を空けていたから、
もしかしたら僕はまだ酔っているのかもしれない。
掠めるように離れていった唇の感触が信じられなくて、頬が熱くなる。
「サトリ!その、あー…えっと」
「なんだよ?」
紆余曲折を経て自分の気持ちを伝えたのは、もう大分前。
そして彼から返事を貰ったのも結構前。
だからと言って何が変わったわけでもなく、
僕たちは旅立った頃と同じように日々を過ごしていた。
それで満足していると言ったら嘘になるかもしれないけれど、
僕たちにはそれが一番のような気がして、キスさえしたことがなかった。
正直言うと、手を握ったこともない。
「サトリ、…あ、―――あ」
「あ?」
ここで僕に甲斐性とやらがあったのなら。
『愛してる』と抱擁一つに、こちらこそよろしくと、爽やかに応じられたのかもしれない。
だが、現実はそんなに甘くない。
『あ』という母音を繰り返し、やっとのことで出てきた言葉は、
甲斐性だとか、そんなものの微塵も感じられないものだった。
「あ、あけま…して、おめ、でとう…」
「?……ん、おめでとう」
情けなくて、いつもの倍の速さで着替えると、
先に行ってるからと、後ろを振り返らずに部屋を飛び出した。
部屋に残されて、思わず溜息が零れる。
「俺の努力、無駄にすんじゃねぇよ…」
一世一代の勇気を振り絞っての行動だったというのに。
相手は、こちらの上を行く奥手だったようだ。
しかし。かく言う自分も、今になって頬が熱くなってきているのだから、
人のことは言えないのかもしれない。
自分のとった行動の恥ずかしさに、後悔が募る。
でも。
彼が言った、『新年の挨拶』。
本当は何と言おうとしていたのだろう。
耳まで赤くしていたのを思い出し、
「今夜あたり、問い詰めてやるか」
ふと笑みが零れた。